【現場で使える】疑義照会の正しい書き方完全ガイド|トラブルを避ける実践テクニック
薬剤師法第24条に基づく疑義照会の正しい実施方法を徹底解説。記録の書き方、医師とのコミュニケーション術、トラブル回避のテクニックまで、現場で即座に活用できる実践ガイドです。
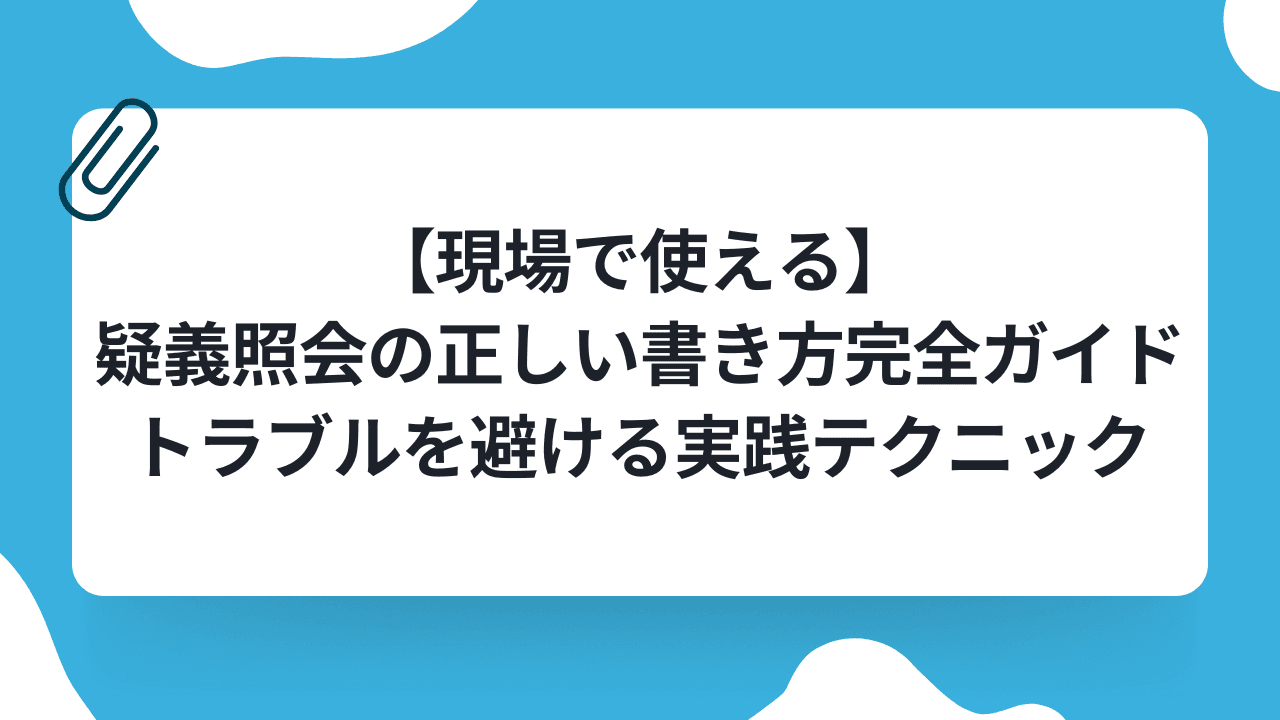
疑義照会は薬剤師の最重要業務|なぜ正しい実施が必要なのか
疑義照会は薬剤師法第24条により定められた法的義務で、処方箋に疑わしい点があるときは医師に問い合わせて確認しなければなりません。全処方箋の約2.74〜3.5%で疑義照会が発生し、そのうち約70%で処方変更が行われているという統計からも、患者安全確保における重要性が分かります。
しかし、実際の現場では「どのように記録すればよいか分からない」「医師とのやり取りで気まずくなる」「時間がかかって業務が滞る」といった課題があります。また、記録の不備により法的問題が生じたり、不適切なコミュニケーションにより医師との関係が悪化したりするリスクも存在します。
この記事では、疑義照会を適切かつ効率的に実施するための具体的な方法を、法的根拠から実践テクニックまで包括的に解説します。年間236億円の医療費削減効果を生む疑義照会を、あなたの薬局でも確実に実施できるようになります。
疑義照会の法的根拠と義務|薬剤師が知るべき基本事項
薬剤師法第24条では「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と明確に規定されています。
この法的義務は形式的な確認だけでなく、用法・用量の適正性、相互作用の確認等の実質的な内容も含む包括的なものです。疑義照会を怠って調剤し、患者に健康被害が生じた場合、薬剤師の法的責任が問われる可能性があります。一方で、適切な疑義照会により医師の処方を変更できる法的権限を有するのは薬剤師だけであり、患者安全の最後の砦としての重要な役割を担っています。
疑義照会の種類と分類|発生パターン別対応法
種類 | 発生頻度 | 主な内容 | 緊急度 |
|---|---|---|---|
重複投薬関連 | 最多 | 同一薬剤の重複、薬理作用類似薬の重複 | 中〜高 |
相互作用関連 | 高頻度 | 禁忌の組み合わせ、併用注意薬剤 | 高 |
用法・用量関連 | 高頻度 | 記載不備、年齢・体重による過量投与 | 中〜高 |
患者背景関連 | 中頻度 | アレルギー歴、妊娠・授乳期への影響 | 高 |
残薬調整 | 中頻度 | 過剰な残薬がある場合の調整 | 低 |
処方記載ミス | 16.2% | 判読不能、薬剤名間違い | 中 |
疑義照会の発見タイミングは、処方箋受付時が52.6%、患者の薬歴確認時が22.4%、服薬指導時が21.1%となっています。早期発見により患者の待ち時間短縮と業務効率化が図れるため、受付時の初期チェックを徹底することが重要です。
薬学的疑義照会は全体の78.1%を占め、そのうち74.88%で処方変更が生じています。これは薬剤師の専門的判断が患者の治療に直接貢献していることを示しており、積極的な疑義照会の実施が患者利益につながります。
正しい記録の書き方|法的要件を満たす記録項目
必須記録項目 | 記録内容 | 記録例 |
|---|---|---|
日時・連絡方法 | 照会した年月日、時間、連絡手段 | 2024/6/6 14:30 電話にて |
疑義の根拠 | 疑義が生じた理由と根拠情報 | お薬手帳にてロキソニンとの重複投薬確認 |
照会内容 | 医師への具体的な問い合わせ内容 | 「ボルタレン錠25mg×3錠 分3毎食後の処方について」 |
医師の回答 | 医師からの回答内容を正確に記録 | 「ロキソニンを中止してボルタレンに変更」 |
最終的な対応 | 実際に行った調剤内容 | 処方変更後のボルタレン錠を調剤・交付 |
患者への説明 | 患者への説明内容と反応 | 重複投薬回避の理由を説明し了承得る |
記録は薬歴の一部として扱われ、最終記入日から起算して3年間の保管が法的に義務付けられています。電子薬歴の場合は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に従い、真正性・見読性・保存性を確保した管理が必要です。
記録する際は、疑義照会に至った経緯を第三者が理解できるよう詳細に記載することが重要です。特に、患者から聴取した情報、お薬手帳の内容、過去の薬歴との比較検討過程を明確に記録することで、後日の振り返りや監査時の説明責任を果たすことができます。
医師とのコミュニケーション術|関係悪化を防ぐ話し方
場面 | 避けるべき表現 | 適切な表現 |
|---|---|---|
照会開始時 | 「処方に間違いがあります」 | 「○○様の処方内容について確認させていただきたいことがあります」 |
疑義の指摘 | 「これは禁忌です」 | 「お薬手帳で○○との併用が確認されますが、いかがいたしましょうか」 |
代替案提示 | 「○○に変更してください」 | 「○○という選択肢もございますが、いかがでしょうか」 |
照会終了時 | 「分かりました」 | 「ご確認いただき、ありがとうございました」 |
医師への照会時は、必ず所属と名前を名乗り、医師の都合を確認してから要点を簡潔に伝えます。疑義照会は医師の診療行為への「間違いの指摘」ではなく、「患者安全のための確認作業」であることを前提とした丁寧なコミュニケーションが重要です。
照会内容を伝える際は、事前に要点をメモにまとめ、患者情報、処方内容、疑義の根拠、可能であれば代替案を順序立てて説明します。医師が忙しい場合でも、要点を早い段階で伝えることで効率的な対応が可能になります。
患者への説明とフォロー
患者に対しては「医師に問い合わせをします」と決めつけるような表現は避け、「より安全にお薬をお使いいただくために確認させていただきます」といった前向きな説明を心がけます。疑義照会のメリットを患者に理解してもらい、可能な限り患者の同意を得てから実施することが望ましいです。
トラブル回避の実践テクニック|効率的な疑義照会の進め方
緊急度判定基準表
緊急度 | 判定基準 | 対応時間 | 対応方法 |
|---|---|---|---|
高 | 生命に関わる相互作用・禁忌 | 即座 | 電話で直接医師に連絡 |
中 | 過量投与・重複投薬 | 30分以内 | 電話またはFAXで連絡 |
低 | 残薬調整・軽微な記載不備 | 1時間以内 | FAXまたは翌日対応可 |
忙しい時間帯での効率的な疑義照会には事前準備が重要です。照会内容を整理したメモを準備し、薬局内でシミュレーションを繰り返すことで、実際の照会時間を大幅に短縮できます。また、よくある疑義照会パターンについては、標準的な対応フローを作成しておくことで迅速な対応が可能になります。
医師不在時の対応策
医師が不在の場合は、患者に状況を説明し、具体的な待機時間(5分なのか30分なのか)を明確に伝えます。代替選択肢として、照会後の電話連絡、薬剤の自宅配達、一部薬剤の先行交付などを提示し、患者の都合に応じた柔軟な対応を行います。
最新動向と効率化|電子処方箋時代の疑義照会
電子処方箋の導入により、形式的な不備による疑義照会の減少が期待されています。2025年3月末の導入率は医療機関で1割に届かない見込みですが、将来的にはリアルタイムでの重複投薬・禁忌薬剤チェックが可能になり、薬学的疑義照会により集中できる環境が整います。
AI・DI支援システムの活用も進んでおり、電子処方箋管理サービスでの項目不備チェック機能により、薬剤師はより高度な薬学的判断に注力できるようになります。ただし、最終的な判断と責任は薬剤師にあることに変わりはなく、システムを適切に活用しながら専門性を発揮することが求められます。
調剤報酬での評価
2024年調剤報酬改定でも重複投薬・相互作用等防止加算が継続され、残薬調整以外で処方変更があった場合は40点、残薬調整の場合20点の加算が維持されています。適切な疑義照会は患者安全確保と同時に、薬局経営にも貢献する重要な業務として位置づけられています。
疑義照会の経済効果と社会的意義
効果項目 | 年間削減額 | 削減内容 |
|---|---|---|
薬剤費節減 | 103億円 | 重複投薬回避、残薬調整等 |
副作用重篤化回避 | 133億円 | 医療費増加の防止 |
合計削減効果 | 236億円 | 2014年度推計値 |
疑義照会による医療費削減効果は年間約236億円と推計され、薬剤師の専門的判断が医療経済にも大きく貢献しています。これは薬剤師約31万人で実現している効果であり、一人当たり年間約76万円の医療費削減に寄与していることになります。
まとめ|確実で効率的な疑義照会の実現に向けて
疑義照会は薬剤師法により定められた法的義務であると同時に、患者安全確保と医療費適正化の両面で重要な役割を果たしています。適切な記録の作成、丁寧なコミュニケーション、効率的な業務フローの確立により、トラブルを避けながら質の高い疑義照会を実施することが可能です。
特に重要なのは、疑義照会を「医師の間違い探し」ではなく「患者安全のためのチームワーク」として捉えることです。医師との良好な関係を維持しながら、薬剤師の専門性を発揮して患者の最善の利益を追求する姿勢が求められます。
電子処方箋やAI支援システムの導入により業務環境は変化していますが、薬剤師の専門的判断と責任の重要性は変わりません。この記事で紹介した実践テクニックを活用し、自信を持って疑義照会に取り組んでください。適切な疑義照会の実施は、患者の信頼獲得と薬剤師の職能向上につながる重要な業務です。