薬剤師はAIで消えるのか:求人・年収・現場が示す将来性の結論
「薬剤師は将来なくなる」という不安の真相を、厚生労働省の最新統計と2045年需給予測データから徹底分析。AI・ロボット導入の実態、供給過剰問題、生き残るための5つの条件と年代別アクションプランを具体的に解説します。
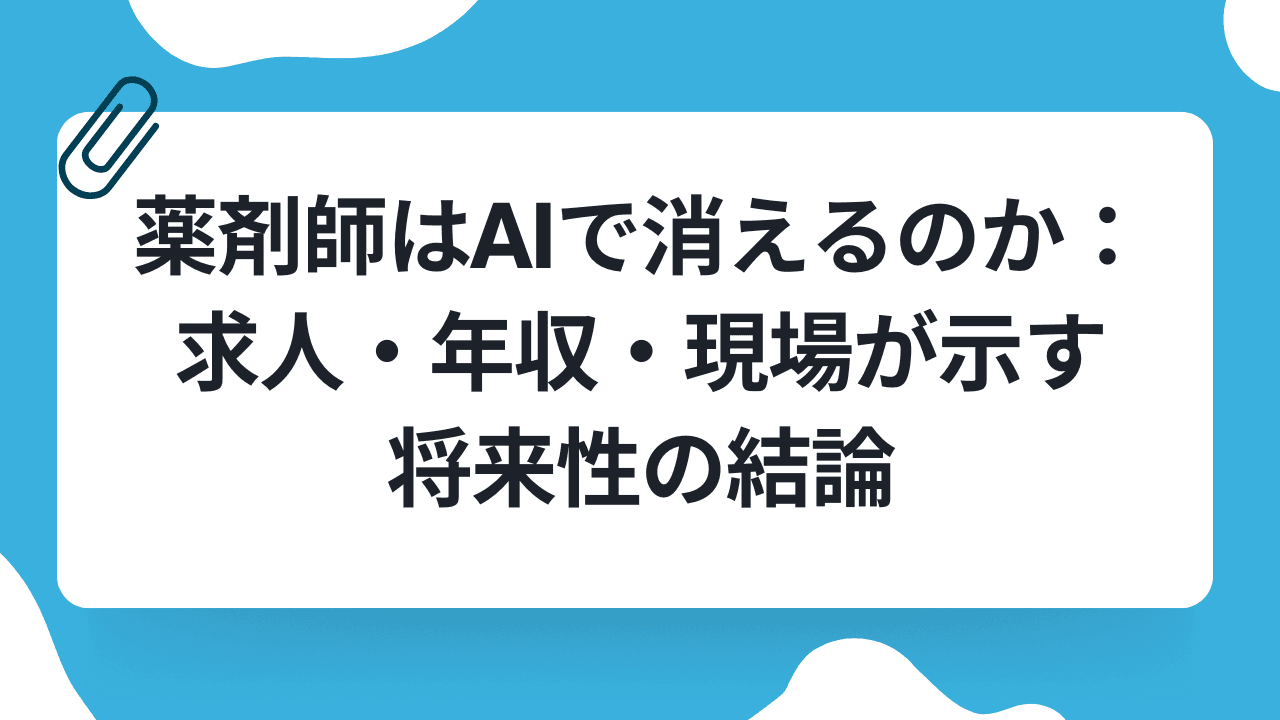
薬剤師は本当に将来なくなるのか?データで見る現実
「薬剤師は将来なくなる職業なのではないか」という不安を抱えていませんか?調剤業務のAI化、供給過剰のニュース、0402通知による登録販売者の業務拡大など、薬剤師を取り巻く環境は確かに厳しさを増しています。
しかし結論から言えば、薬剤師という職業が完全になくなることはありません。ただし、「どんな薬剤師でも安泰」という時代は確実に終わりました。本記事では、厚生労働省の最新統計データと2045年までの需給予測を基に、薬剤師の将来性の真実と生き残るための具体的な戦略を解説します。
薬剤師が「なくなる」と言われる3つの理由
理由1:供給過剰による需給バランスの崩壊
厚生労働省の「薬剤師需給推計」によれば、2045年には深刻な供給過剰が予測されています。
年度 | 薬剤師供給数 | 薬剤師需要数 | 過剰人数 |
|---|---|---|---|
2020年 | 321,982人 | ほぼ均衡 | ― |
2022年 | 323,690人 | ほぼ均衡 | ― |
2045年(現状維持) | 458,000人 | 332,000人 | 126,000人 |
2045年(業務拡大) | 432,000人 | 408,000人 | 24,000人 |
出典:厚生労働省「令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計」「薬剤師需給推計」
現在のペースで薬学部卒業生が増え続けると、2045年には最大12.6万人の薬剤師が余る計算です。業務範囲を拡大したとしても、約2.4万人の過剰が予測されています。
実際、都市部の調剤薬局では既に求人倍率が低下しており、「薬剤師なら引く手あまた」という時代は終わりつつあります。
理由2:AI・ロボットによる調剤業務の自動化
調剤業務の自動化は急速に進んでいます。以下は実際の導入事例です。
企業・薬局 | 導入時期 | 自動化内容 | 効果 |
|---|---|---|---|
トモズ松戸新田店 | 2019年 | 調剤ロボット7種9台導入 | 調剤業務の90%自動化、一包化作業30-60分→3分 |
メディカルユアーズ | 2023年 | ロボット薬局システム | 調剤ミス件数ゼロ、待ち時間ゼロを実現 |
MG-DX(サイバーエージェント) | 2024年 | 対話型AIアシスタント | 受付・接客業務の自動化 |
なのはな薬局鶴川通り店 | 2025年 | 接客ロボット導入 | カスハラ対策、薬剤師の業務負担軽減 |
出典:各社プレスリリース、日経ビジネス
特に注目すべきは、トモズが調剤業務の90%を自動化した事例です。ただし、これは「一包化や錠剤ピッキングなど特定作業」の自動化であり、服薬指導や薬歴管理、疑義照会といった対人業務は依然として薬剤師が担っています。
理由3:登録販売者の業務範囲拡大
2019年4月の0402通知により、登録販売者が薬剤師の管理下で一部の調剤補助業務を実施できるようになりました。具体的には以下の業務です。
- 調剤された薬剤の数量確認
- 一包化された薬剤の監査補助
- 調剤録・薬剤服用歴への入力補助
これにより、薬剤師1人あたりが監督できる業務範囲が拡大し、「薬剤師の配置人数を減らせる」という見方が広がっています。
それでも薬剤師がなくならない5つの理由
不安材料ばかりを見てきましたが、薬剤師という職業が完全になくなることはありません。その根拠を5つのデータで示します。
1. 法律で守られた独占業務
薬剤師法第19条により、調剤行為は薬剤師にしかできない独占業務です。AI・ロボットが発達しても、最終的な調剤責任と服薬指導は必ず薬剤師が行う必要があります。
2. 高齢化による医療需要の増大
2025年には団塊の世代が全員75歳以上となり、医療・介護需要は急増します。特に在宅医療における薬剤師の需要は拡大傾向です。
年度 | 75歳以上人口 | 医療費(兆円) | 在宅医療需要 |
|---|---|---|---|
2020年 | 1,872万人 | 42.2兆円 | 増加傾向 |
2025年 | 2,180万人 | 47.4兆円(予測) | 急増 |
2040年 | 2,239万人 | 66.7兆円(予測) | ピーク |
出典:厚生労働省「医療費の動向」「高齢者人口推計」
3. 専門薬剤師・認定薬剤師の需要拡大
がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師、糖尿病療養指導士など、専門資格を持つ薬剤師の需要は増加しています。特に病院薬剤師では専門資格の有無が採用条件となるケースも増えています。
4. 対人業務は自動化できない
服薬指導、患者とのコミュニケーション、多職種連携といった対人業務は、AIでは代替できません。むしろ対物業務が自動化されることで、薬剤師は対人業務に専念できる環境が整いつつあります。
5. 地方では依然として薬剤師不足
供給過剰は主に都市部の問題です。地方では依然として薬剤師不足が深刻であり、求人倍率は都市部の2倍以上となっています。
地域区分 | 薬剤師求人倍率 | 平均年収 | 状況 |
|---|---|---|---|
東京23区 | 1.2倍 | 550万円 | 供給過剰傾向 |
地方都市 | 3.5倍 | 600万円 | やや不足 |
過疎地域 | 5.0倍以上 | 650万円以上 | 深刻な不足 |
出典:薬キャリ、マイナビ薬剤師(2024年データ)
将来も活躍できる薬剤師になるための5つの条件
これからの時代を生き抜くために、薬剤師が身につけるべき5つの条件を解説します。
条件1:専門性を磨く
専門・認定薬剤師資格を取得し、特定領域のエキスパートになることが重要です。特に需要が高い分野は以下の通りです。
- がん専門薬剤師:がん治療の複雑化により需要増
- 感染制御専門薬剤師:AMR対策で病院からの需要が高い
- 精神科専門薬剤師:メンタルヘルス需要の増加
- 緩和薬物療法認定薬剤師:在宅医療で必須
条件2:在宅医療スキルを身につける
2025年以降、在宅医療の需要は急増します。訪問服薬指導、多職種連携、医療機器の知識など、在宅医療に必要なスキルを習得することが差別化につながります。
条件3:対人コミュニケーション能力を高める
AIには代替できない「患者の微妙な変化に気づく力」「信頼関係を構築する力」が重要です。薬学的知識だけでなく、傾聴力、共感力、説明力を磨きましょう。
条件4:IT・DXスキルを習得する
電子薬歴、オンライン服薬指導、処方箋の電子化など、薬局DXは加速しています。ITツールを使いこなせる薬剤師は、業務効率が高く評価されます。
条件5:地方・過疎地での勤務も視野に入れる
都市部で競争が激化する中、地方では依然として薬剤師不足です。地方勤務を選択することで、高年収と安定したキャリアを築けます。
年代別:今すぐ始めるべきアクションプラン
20代薬剤師がすべきこと
専門性の土台を作る時期です。以下のアクションを推奨します。
- 認定薬剤師資格の取得(研修認定薬剤師など)
- 在宅医療経験を積める職場への転職
- 病院薬剤師として専門性を磨く選択肢も検討
- 学会発表や論文執筆で実績を作る
30代薬剤師がすべきこと
専門性を確立し、マネジメント経験を積む時期です。
- 専門薬剤師資格の取得(がん、感染制御など)
- 管理薬剤師やエリアマネージャーへのキャリアアップ
- 在宅医療の実践経験を増やす
- 転職するなら「専門性」か「マネジメント」の軸を明確に
40代以上の薬剤師がすべきこと
専門性を活かし、後進育成にも貢献する時期です。
- 既存の専門性をさらに深掘りし、地域で「あの分野ならこの薬剤師」と言われる存在になる
- 管理職としてチームマネジメント力を磨く
- 地方薬局への転職で高年収を実現する選択肢も
- オンライン服薬指導など新しい働き方にも挑戦
まとめ:薬剤師は「なくならない」が「選ばれる時代」へ
薬剤師という職業がなくなることはありませんが、「薬剤師なら誰でも安定」という時代は終わりました。
2045年には最大12.6万人の供給過剰が予測される中、生き残るためには「専門性」「対人スキル」「地域医療への貢献」が必須です。調剤業務の90%が自動化された事例もありますが、それは薬剤師が対人業務に専念できる環境が整ったとも言えます。
今から行動を始めることで、将来も必要とされる薬剤師になれます。20代なら専門性の土台作り、30代なら専門資格とマネジメント経験、40代以上なら専門性の深掘りと後進育成。年代に応じた戦略的なキャリア構築が、あなたの将来を守ります。
よくある質問(FAQ)
Q1. AIやロボットで薬剤師の仕事は本当になくなりますか?
A. 調剤業務の一部(一包化、ピッキングなど)は自動化が進んでいますが、服薬指導、疑義照会、薬歴管理といった対人業務は薬剤師にしかできません。トモズの事例では調剤業務の90%が自動化されましたが、これは「特定作業」の自動化であり、薬剤師の仕事全体の90%ではありません。むしろ対物業務が自動化されることで、薬剤師は対人業務に専念できるようになります。
Q2. 2045年に12万人も余るなら、今から薬剤師を目指すのは危険ですか?
A. 供給過剰は主に都市部の問題であり、地方では依然として薬剤師不足が続いています。また、専門薬剤師や在宅医療に強い薬剤師は引く手あまたです。重要なのは「どこで」「どんな専門性を持って」働くかです。戦略的にキャリアを構築すれば、十分に活躍できます。
Q3. 登録販売者に仕事を奪われませんか?
A. 登録販売者ができるのは「調剤補助業務」であり、調剤行為そのものは薬剤師法により薬剤師の独占業務です。0402通知で業務範囲は拡大しましたが、最終責任は必ず薬剤師が負います。むしろ登録販売者と連携することで、薬剤師はより高度な業務に集中できるようになります。
Q4. 薬剤師として生き残るために最も重要なスキルは何ですか?
A. 専門性と対人コミュニケーション能力の2つです。専門薬剤師資格を取得して特定領域のエキスパートになること、そして患者・多職種と信頼関係を築けるコミュニケーション能力が、AIには代替できない価値を生み出します。
Q5. 今から専門薬剤師を目指すのは遅いですか?(40代)
A. 遅くありません。専門薬剤師の受験資格には実務経験が必要なため、むしろ40代は豊富な経験を活かせる年代です。がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師などは、40代以上の取得者も多数います。
Q6. 地方勤務を考えていますが、キャリアアップできますか?
A. 地方でも十分にキャリアアップできます。むしろ地方では薬剤師不足のため、管理薬剤師やエリアマネージャーへの昇進が早い傾向があります。また在宅医療の需要が高く、専門性を磨く機会も豊富です。年収も都市部より高いケースが多いため、キャリアと収入の両面でメリットがあります。
Q7. 転職すべきタイミングはいつですか?
A. 以下のタイミングが転職の好機です。
・専門性を身につけたいが、今の職場では経験を積めない
・在宅医療に挑戦したいが、対応していない薬局にいる
・管理薬剤師を目指しているが、ポストが空いていない
・都市部で求人倍率が下がる前に、地方の高年収求人を狙いたい
特に20代・30代は専門性を身につけるための転職が有効です。40代以上は専門性を活かせる職場、または管理職としてマネジメント経験を積める職場への転職を検討しましょう。