エフィエント錠のGS1コード誤表示が発覚 バーコード鑑査システム導入薬局への影響と対応
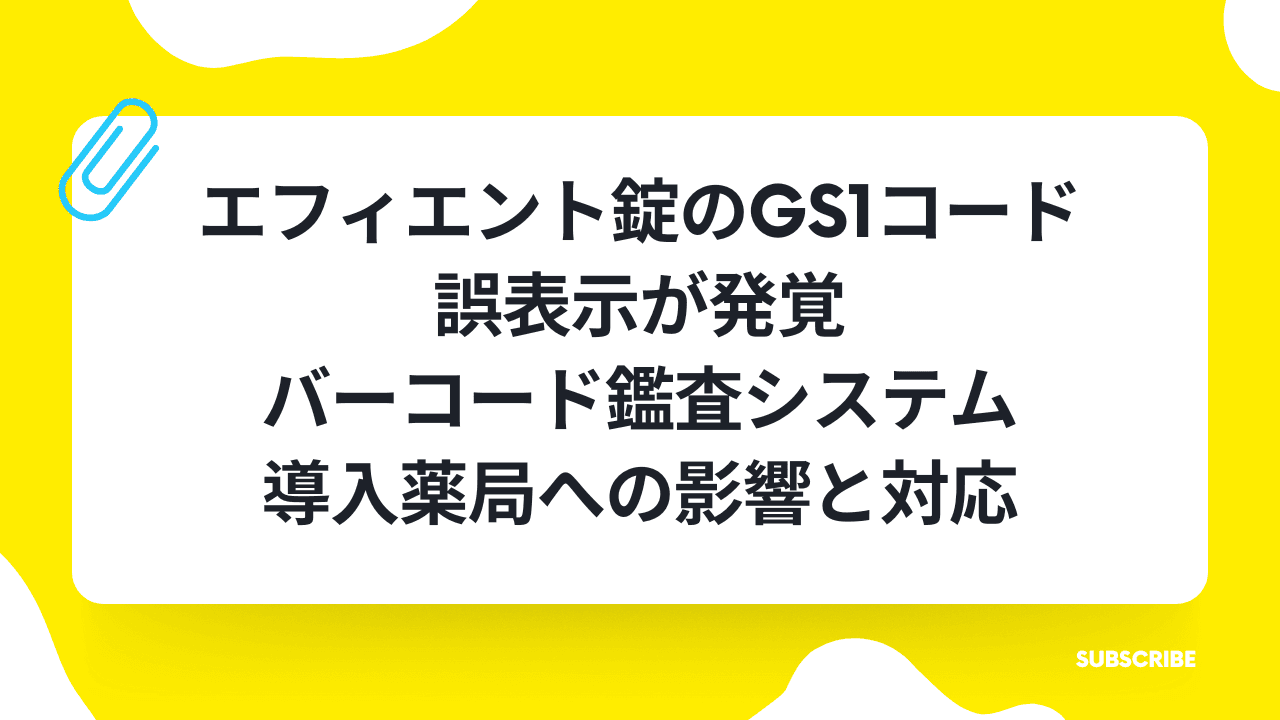
エフィエント錠のGS1コード誤表示が発覚 薬剤師の対応が求められる事態に
2025年9月、第一三共株式会社が製造販売する抗血小板剤「エフィエント錠3.75mg」(一般名:プラスグレル塩酸塩)のPTPシートに、抗凝固薬「リクシアナ錠15mg」(エドキサバントシル酸塩水和物)のGS1コード(調剤包装単位コード)が誤って印字されていることが判明しました。
第一三共は9月25日に本件を公表し、日本薬剤師会も都道府県薬剤師会担当役員宛に注意喚起文書を発出したと報じられています。薬剤の品質自体には問題がないものの、バーコード鑑査システムを導入している薬局では業務への影響が避けられない状況となっています。
誤表示の詳細と対象製品
何が誤っているのか
今回の事案で誤表示となっているのは、PTPシートに印字された「GS1コード(調剤包装単位コード)」です。エフィエント錠3.75mgのPTPシートに、本来とは異なるリクシアナ錠15mgのGS1コードが印字されています。
重要なポイントとして、以下の点が挙げられます。
- PTPシートに充填されている錠剤は正しくエフィエント錠3.75mgである
- 商品名の表示は正しい
- 販売包装単位と元梱包装単位のGS1コードは正しい
- PTPシートの調剤包装単位コードのみが誤っている
対象ロット
医療専門メディアの報道によると、対象となるのは以下の製造番号の製品です。
包装単位 | 対象製造番号 |
|---|---|
PTP 100錠 | TDA0249以降 |
PTP 500錠 | TDA0260以降 |
PTP 140錠 | TDB0253以降 |
PTP 700錠 | TDC0253以降 |
詳細は第一三共株式会社の公式発表をご確認ください。
第一三共の対応方針
通常であれば即時回収が必要な事案ですが、第一三共は当面回収を行わない方針を示しています。その理由として、治療上当該製品からの代替が困難なケースが想定されること、PTPシートに充填されている錠剤には誤りがなく商品名も正しく表示されていることを挙げています。
正しいGS1コードを印字した訂正品は2025年12月頃の出荷を予定していると報じられており、安定供給に支障がない状況となり次第、速やかに自主回収を実施するとしています。
バーコード鑑査システムへの影響
システムが誤認識する仕組み
GS1コードは、2022年12月から医療用医薬品へのバーコード表示が義務化された調剤包装単位ごとのコードです。バーコードリーダーでこのコードを読み取ることで、医薬品の取り違え防止や有効期限・ロット番号の管理が効率的に行えるようになっています。
しかし今回の事案では、エフィエント錠のPTPシートをスキャンした際に、システムが「リクシアナ錠15mg」として認識してしまいます。この2つの薬剤は薬効分類が異なります。
項目 | エフィエント | リクシアナ |
|---|---|---|
薬効分類 | 抗血小板剤 | 抗凝固薬 |
一般名 | プラスグレル塩酸塩 | エドキサバントシル酸塩水和物 |
想定される業務への影響
バーコード鑑査システムを導入している薬局では、以下のような影響が考えられます。
調剤鑑査での混乱
処方箋にはエフィエント錠と記載されているにもかかわらず、バーコードリーダーで読み取ると「リクシアナ錠15mg」と表示されます。システムによっては「薬剤不一致」のエラーが表示され、調剤作業が一時停止する可能性があります。
在庫管理システムの不整合
バーコードで入庫・出庫処理を行っている薬局では、エフィエント錠を出庫したにもかかわらず、システム上はリクシアナ錠の在庫が減少することになります。その結果、在庫データと実在庫に差異が生じ、発注ミスや棚卸時の混乱を招く恐れがあります。
電子薬歴への誤記録
服薬指導時にバーコードで薬剤情報を読み取る運用をしている場合、電子薬歴に「リクシアナ錠15mg」と誤って記録される可能性があります。後日の薬歴確認時に混乱を招くだけでなく、データベースの信頼性にも影響を与えかねません。
薬局での対応方法
即時対応が推奨される事項
日本薬剤師会の注意喚起を踏まえ、薬局では以下の対応が推奨されます。
目視確認の徹底
バーコードシステムはあくまで補助ツールであり、最終確認は薬剤師が行う必要があります。PTPシートの製品名表示と錠剤の印字を目視で確認し、処方箋との照合を慎重に行うことが望ましいとされています。
在庫の確認とロット番号の特定
エフィエント錠3.75mgの在庫がある薬局は、対象ロットに該当するかを確認することが推奨されます。該当する場合は、スタッフ全員に周知し、取り扱いに注意するよう徹底することが望ましいでしょう。
システムベンダーへの相談
使用している調剤システムによって対応方法が異なります。ベンダーに連絡し、マスタデータの修正方法や代替手順について確認することが推奨されます。第一三共が提供する文書に印字された正しいGS1コードを読み取ることで対処できる場合もあるとされています。
患者への説明
バーコード確認に時間がかかり、調剤の待ち時間が延長する可能性があります。患者から質問があった場合は、厚生労働省や日本薬剤師会の公式情報を基に、「バーコードに誤りがあるが、お薬の中身は正しいエフィエント錠である」ことを丁寧に説明することが推奨されます。
中長期的な対応
訂正品の出荷は2025年12月頃を予定していると報じられています。それまでの間は目視確認を継続し、訂正品の入荷後は速やかに切り替えを行うことが望ましいでしょう。また、自主回収が開始された際には、メーカーからの連絡に従って対応する必要があります。
デジタル時代の薬剤師に求められるスキル
システムトラブル対応力の重要性
今回の事案は、電子処方箋やオンライン服薬指導など、薬局業務のデジタル化が進む中で、システムへの過度な依存のリスクを浮き彫りにしました。バーコードシステムは調剤過誤の防止に大きく貢献していますが、完璧ではありません。
厚生労働省の調査(令和元年度)によると、バーコードシステムを利用する薬局では、利用しない薬局に比べて調剤漏れや取り違えなどのミスが少ないことが報告されています。実際の導入事例では、薬剤師のエラーによる薬剤の取り違いをほぼゼロに減らすことができたケースもあります。しかし、システムに不具合が発生した際に適切に対応できなければ、かえってリスクが高まる可能性があります。
GS1コードの理解深化
GS1コードは単なるバーコードではなく、医薬品のトレーサビリティを確保するための重要なインフラです。薬剤師は以下のような知識を身につけることで、システムトラブルに適切に対応できるようになります。
- GS1コードの構造と仕組み(AIコード、チェックデジットなど)
- 調剤包装単位と販売包装単位の違い
- バーコードシステムのアーキテクチャとマスタデータ管理
- トラブルシューティングの基本的な手順
キャリア市場での評価
システムトラブルに適切に対応できる薬剤師は、転職市場でも高く評価される傾向があります。特に以下のような経験は、キャリアアップの武器となる可能性があります。
- GS1コード誤り対応などのインシデント管理経験
- システム障害時の代替業務フロー構築
- 電子処方箋やオンライン服薬指導の実務経験
- 調剤システムの導入・運用改善プロジェクトへの参画
デジタルリテラシーを持つ薬剤師と基本的な調剤スキルのみの薬剤師では、転職時の年収提示額に差が見られるケースもあります。ただし、個人の経験やスキル、地域、業態により大きく異なります。
業界全体への示唆と今後の展望
製薬企業の品質管理体制
今回の事案を受け、製薬業界全体で品質管理体制の見直しが進むと予想されます。特に以下の点が強化される可能性があります。
- 印刷工程における複数製品のコード混入防止策
- AI・画像認識技術を活用した印刷検査の自動化
- GS1コードマスタデータの厳格な管理
- 市販後のバーコード監視体制の構築
GS1コード運用の課題
GS1コードの義務化は2022年12月と比較的最近であり、運用上の課題も明らかになりつつあります。今後、以下のような改善が期待されます。
- 厚生労働省主導の統一データベース整備とリアルタイム更新
- メーカーから薬局への緊急情報伝達システムの構築
- ブロックチェーン技術を活用した改ざん防止とトレーサビリティ強化
- AI・機械学習による異常検知とアラート機能
薬剤師教育の変革
今回の事案は、薬学教育と生涯教育の両面で変革の必要性を示しています。大学のカリキュラムにはデジタルヘルスやデータサイエンスの科目を追加し、実務実習ではシステム障害時の対応訓練を取り入れるべきという声も上がっています。
また、薬剤師会や職能団体による認定制度の創設も期待されます。「医療DX推進薬剤師」や「医薬品品質管理認定薬剤師」といった専門資格が整備されることで、薬剤師のスキルアップとキャリア形成の道筋が明確になる可能性があります。
まとめ:システムと人のバランスが鍵
エフィエント錠のGS1コード誤表示事案は、デジタル化が進む薬局業務において、システムへの過度な依存のリスクを改めて認識させる出来事となりました。バーコードシステムは調剤過誤防止に大きく貢献していますが、完璧ではありません。
薬剤師に求められるのは、システムを理解し活用しながらも、最終的な安全確認は人間が行うというバランス感覚です。目視確認の重要性は変わらず、むしろデジタル時代だからこそ、基本に立ち返る姿勢が重要になります。
一方で、システムトラブルに適切に対応できる知識とスキルは、今後のキャリア形成において武器となる可能性があります。GS1コードの仕組みを理解し、インシデント管理の経験を積み、デジタルリテラシーを高めることで、薬剤師としての市場価値向上につながることが期待されます。
今回の事案を学びの機会と捉え、システムと人間の協働による安全な医療の実現を目指していくことが重要です。
免責事項
本記事は薬剤師向けのキャリア情報提供を目的としており、医学的助言や特定の医薬品の使用を推奨するものではありません。医薬品に関する情報は2025年10月時点のものであり、最新の情報は添付文書、インタビューフォーム、PMDAウェブサイト等でご確認ください。
年収や転職市場に関する情報は、一般的な傾向を示したものであり、個人の経験、スキル、地域、勤務先により大きく異なります。転職に関する判断は、ご自身の責任において行ってください。
GS1コード誤表示に関する情報は、第一三共株式会社および日本薬剤師会の公式発表、ならびに医療専門メディアの報道に基づいています。最新の情報や詳細は、各機関の公式ウェブサイトをご確認ください。
関連トレンド情報
エフィエント錠GS1コード誤表示事案
影響度:第一三共が製造販売する抗血小板剤「エフィエント錠3.75mg」のPTPシートに、抗凝固薬「リクシアナ錠15mg」のGS1コードが誤って印字されていることが判明。日本薬剤師会も注意喚起を発出し、バーコード鑑査システム導入薬局では業務への影響が懸念されています。
バーコード鑑査システムを導入している薬局では、エフィエント錠をスキャンした際にリクシアナ錠として認識されるため、調剤鑑査や在庫管理に混乱が生じる可能性があります。目視確認の徹底とシステムベンダーへの相談が推奨されます。
今回の事案は、デジタル化が進む薬局業務において、システムトラブル対応力の重要性を再認識させるものとなりました。GS1コードの仕組みを理解し、インシデント管理の経験を持つ薬剤師は、転職市場でも高く評価される傾向があります。
GS1コード義務化とバーコードシステムの課題
影響度:2022年12月に医療用医薬品へのGS1コードバーコード表示が義務化されましたが、今回のような印字ミスが発生すると、調剤過誤防止システムが逆に混乱の原因となるリスクが浮き彫りになりました。
GS1コードは医薬品の取り違え防止とトレーサビリティ確保を目的としていますが、印刷工程での品質管理が重要であることが改めて認識されました。製薬業界全体で、AI・画像認識技術を活用した印刷検査の自動化など、品質管理体制の強化が進むと予想されます。
薬剤師にとっては、GS1コードの構造や仕組みを理解することで、システムトラブル時に適切に対応できるスキルが身につきます。デジタルリテラシーを持つ薬剤師の需要は今後さらに高まる可能性があります。
電子処方箋時代のシステム依存リスク
影響度:2025年時点で薬局の81.3%が電子処方箋の運用を開始しており、バーコードシステムとの連携が進んでいます。しかし今回の事案は、システムへの過度な依存のリスクと、最終確認は人間が行う重要性を示しました。
電子処方箋やオンライン服薬指導など、薬局業務のデジタル化が急速に進む中、システムトラブルへの対応力が薬剤師に求められています。システムを理解し活用しながらも、最終的な安全確認は人間が行うというバランス感覚が重要です。
システム障害時の代替業務フロー構築や、電子処方箋・オンライン服薬指導の実務経験を持つ薬剤師は、転職市場での評価が高まる傾向にあります。DX推進の波に乗り遅れないよう、継続的なスキルアップが推奨されます。