厚生労働省が医薬品供給問題の行動計画を策定、卸・薬局等の対応指針を明確化
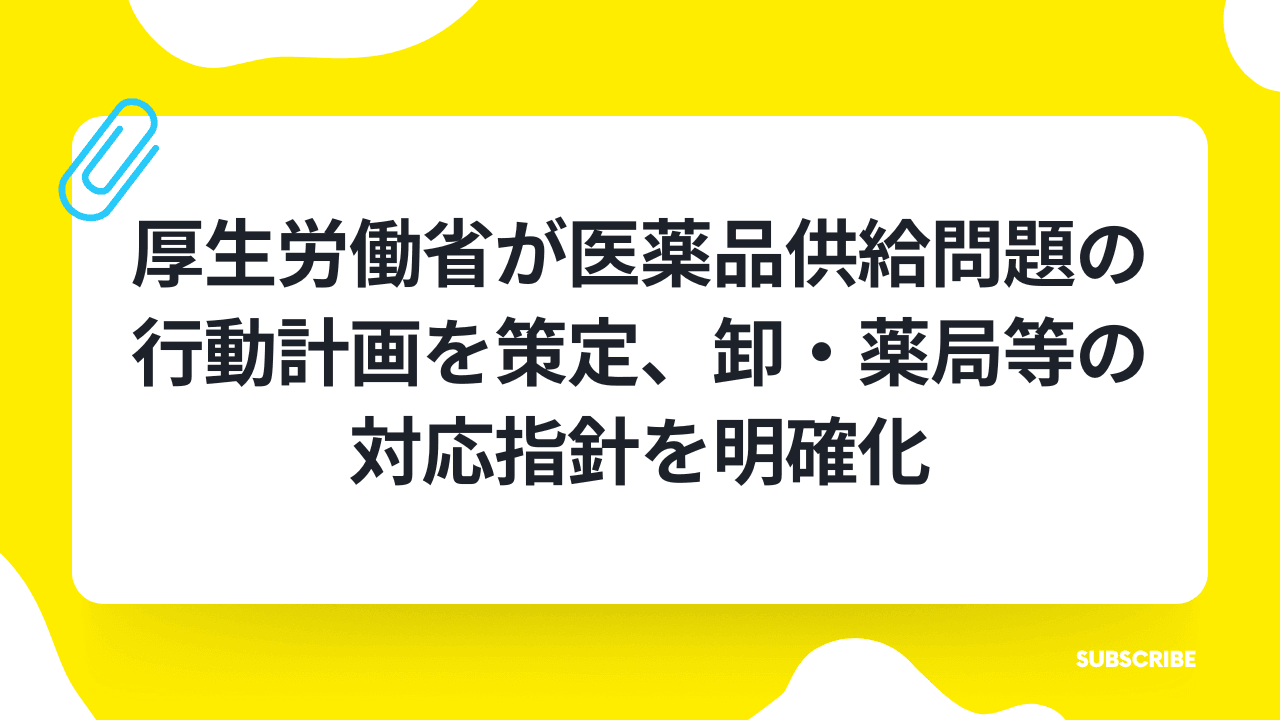
行動計画策定の背景と概要
厚生労働省は2025年9月25日、医療用医薬品の供給問題への対応にかかる行動計画を策定しました。この計画は、2024年度事業「医薬品供給リスク等調査・分析事業」における安定供給に関する有識者の意見を踏まえ、医薬品の安定供給にかかるリスクシナリオを整理した上で、医薬品供給の各関係主体が医薬品供給問題への対応を行う際の基本的な行動指針をまとめたものです。
医薬品供給不足は2020年頃から顕在化し、2025年2月18日時点での厚生労働省の発表では、通常出荷されていない医薬品の割合は約21.9パーセントに達しています。そのうち後発医薬品の割合が約60パーセント、先発医薬品や長期収載医薬品も12.7パーセントという深刻な状況が続いています。
医薬品供給不足の主な原因
医薬品供給不足の背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。
品質問題による製造停止
2020年頃より顕在化した後発医薬品メーカーの品質問題による行政処分が大きな要因となっています。製造管理・品質管理の不備により、複数の製造拠点が操業停止を余儀なくされ、市場への供給が大幅に減少しました。
原材料確保の困難性
海外からの原薬供給に依存している医薬品が多く、国際情勢の変化や為替変動の影響を受けやすい構造的な脆弱性があります。特に中国やインドからの原薬供給が滞ると、国内製造にも大きな影響が出ます。
製造設備の老朽化
長年にわたり製造してきた医薬品の製造設備が老朽化し、突発的な故障による生産停止のリスクが高まっています。特に後発医薬品は薬価が低く、設備投資が十分に行われてこなかった側面があります。
新型コロナウイルス感染症の影響
パンデミックによる需要急増と供給網の混乱も、医薬品不足を加速させる要因となりました。一部の医薬品では需要予測を大きく上回る処方が続き、在庫配分の偏在も生じています。
行動計画における各主体の役割
国の役割
国は、医薬品の安定供給確保のために平時より供給状況に関する情報収集を実施し、必要な情報を他主体に発信することが定められました。具体的には、収集した情報をもとに関係者と協力しながら医薬品の安定供給に向けて、必要な対策を企画立案・実行することが求められます。
2025年には、医薬品の製造から患者への調剤までを追跡できる新しいシステムの開発も計画されています。このシステムは電子処方箋管理サービスのデータを活用し、医薬品会社や医薬品卸のデータと組み合わせることで、ほぼリアルタイムで医薬品の使用状況を把握できるようになります。
医薬品卸売業者の役割
卸売業者には、市場全体の需給バランスを見ながら適正な在庫配分を行うことが期待されています。特定の医療機関や薬局への過度な集中配送を避け、地域全体で公平な医薬品供給を実現する責任があります。
薬局の役割
薬局には、供給不足が発生した際の柔軟な対応が求められます。2024年3月に厚生労働省が発出した通知により、後発医薬品が処方された場合でも、供給不足時には患者の同意を得た上で先発医薬品への変更調剤が認められるようになりました。
また、在庫の適正管理も重要な役割となります。過剰な在庫確保は他の薬局での供給不足を招く可能性があるため、適切な発注量を心がける必要があります。
薬剤師の実務への具体的影響
変更調剤の柔軟化
2024年3月以降、後発医薬品から先発医薬品への変更調剤において、処方医への確認が不要となりました。ただし、患者への丁寧な説明と同意取得は必須です。薬剤師には、供給状況を踏まえた適切な代替薬提案と、患者の経済的負担への配慮が求められます。
先発医薬品への変更により患者負担が増加する場合、その理由と必要性を分かりやすく説明するコミュニケーション能力が重要になります。
在庫管理の高度化
供給不足の長期化により、薬局での在庫管理がより重要になっています。複数の後発医薬品メーカーの製品を取り扱うことでリスク分散を図ったり、供給状況をリアルタイムで把握するシステムの活用が推奨されます。
日本製薬団体連合会が2024年1月に改訂した「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」では、製造販売業者に3ヶ月以上の在庫確保が求められるようになりましたが、薬局側でも一定期間の需要を見越した計画的な発注が必要です。
調剤業務の効率化
2025年薬機法改正では、一定の要件を満たす薬局間で一包化や錠剤分包などの調剤補助業務を委託できる制度が法制化されました。これにより、供給不足対応や患者対応など、薬剤師が対人業務により多くの時間を割けるようになります。
調剤業務の外部委託を活用することで、供給不足による業務負荷増加に対処しやすくなりますが、委託先との連携体制の構築や品質管理の徹底が求められます。
キャリアへの影響
専門性の向上機会
医薬品供給不足への対応は、薬剤師の専門性を発揮する機会でもあります。代替薬の提案、患者への丁寧な説明、医療機関との連携など、高度な薬学的知識とコミュニケーション能力が求められる場面が増えています。
こうした経験は、薬剤師としての市場価値を高める要因となります。特に供給不足時の適切な対応実績は、転職市場において評価される可能性があります。
業務範囲の拡大
電子処方箋システムの普及や調剤業務の外部委託制度により、薬剤師の業務範囲が変化しています。単純な調剤作業から解放され、服薬指導や薬学的管理により注力できる環境が整いつつあります。
ただし、2025年1月12日時点での電子処方箋対応施設は、病院3.9パーセント、医科診療所9.9パーセント、薬局63.2パーセントにとどまっており、全国普及にはまだ時間がかかる見込みです。
求人市場への影響
医薬品供給不足問題は薬剤師の求人市場に直接的な影響は限定的ですが、薬局経営の厳しさは増しています。2023年の医師・薬剤師の有効求人倍率は2.15倍と、コロナ前の2019年の3.77倍から低下しており、特に都市部では競争が激しくなっています。
一方、地方の薬剤師不足は依然として深刻であり、地域によって需給バランスには大きな差があります。
今後の展望と準備すべきこと
短期的対応(今後1年)
薬局薬剤師は、まず自局で取り扱う医薬品の供給状況を定期的にチェックする体制を整える必要があります。卸売業者との緊密なコミュニケーションを保ち、供給不足が予想される医薬品については早めに代替品を検討しておくことが重要です。
患者への説明スキル向上も急務です。医薬品変更の理由を分かりやすく伝え、不安を軽減するコミュニケーション能力が求められます。
中長期的対応(今後3-5年)
電子処方箋システムの全国普及に伴い、医薬品供給のトラッキングシステムが本格稼働する見込みです。このシステムを活用した需給予測と効率的な在庫管理のスキルが、今後の薬剤師に求められます。
また、調剤業務の外部委託が一般化する中で、対人業務の専門性をより高めることがキャリア形成の鍵となります。服薬指導、薬学的管理、地域医療への貢献など、薬剤師ならではの価値を発揮できる分野での専門性向上が重要です。
政策動向の注視
厚生労働省は今後も医薬品の安定供給に関する施策を継続的に強化していく方針です。2025年度診療報酬改定や薬価制度の見直しなども予定されており、これらが医薬品供給や薬局経営に与える影響を注視する必要があります。
日本製薬団体連合会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会など、業界団体からの情報発信にも常にアンテナを張り、最新の対応方針を把握しておくことが求められます。
実務対応チェックリスト
医薬品供給不足に適切に対応するため、以下の項目を定期的に確認することを推奨します。
- 厚生労働省の医薬品供給状況リストを月1回以上確認
- 卸売業者と週1回以上の供給状況情報交換
- 供給不足が予想される医薬品の代替品リスト作成
- 後発医薬品から先発医薬品への変更調剤手順の整備
- 患者への説明用資料の準備(供給不足の理由、代替薬の情報等)
- 在庫管理システムの活用と発注量の適正化
- 電子処方箋システムへの対応準備
- 調剤業務外部委託の検討(該当する場合)
- スタッフ間での情報共有体制の構築
- 緊急時の医療機関連絡体制の確認
まとめ
厚生労働省による医薬品供給問題の行動計画策定は、薬剤師の実務に直接的な影響を及ぼす重要な政策です。変更調剤の柔軟化、在庫管理の高度化、業務効率化など、現場での対応が求められる場面が増えています。
一方で、この状況は薬剤師の専門性を発揮する機会でもあります。医薬品供給不足という困難な状況下で、患者に最適な薬物療法を提供し続けることが、薬剤師の真価が問われる場面となっています。
今後も政策動向や業界の取り組みを注視しながら、柔軟かつ適切な対応を心がけることが、薬剤師としてのキャリア形成にもつながっていくでしょう。
関連トレンド情報
厚労省が医薬品供給対応の行動計画を策定
影響度:厚生労働省は2025年9月25日、医療用医薬品の供給問題への対応にかかる行動計画を策定しました。2024年度事業「医薬品供給リスク等調査・分析事業」の有識者意見を踏まえ、医薬品供給の各関係主体(国・卸・薬局・病院等)が供給問題に対応する際の基本的な行動指針をまとめたものです。国は平時から供給状況の情報収集を行い、関係者と協力して安定供給のための対策を企画・実行する役割を担います。
この行動計画は、薬剤師の実務に直接影響する重要な政策です。特に薬局薬剤師には、供給不足時の柔軟な変更調剤対応や適正な在庫管理が求められます。卸売業者との密な連携や、患者への丁寧な説明スキルが今まで以上に重要になります。転職を考える際は、医薬品供給不足への組織的な対応体制が整っている職場を選ぶことも、働きやすさの指標となるでしょう。
後発品から先発品への変更調剤が柔軟化
影響度:2024年3月、厚生労働省は後発医薬品の供給不足に対応するため、薬局での変更調剤を柔軟に認める通知を発出しました。後発医薬品が処方された場合でも、供給不足時には患者の同意を得た上で先発医薬品への変更が可能となり、処方医への確認は不要になりました。また、後発医薬品使用体制加算などの計算においても、2025年9月分まで供給不安薬を除外することが認められています。
この変更により、薬剤師の裁量権が拡大し、より迅速な患者対応が可能になりました。ただし、先発品への変更で患者負担が増加する場合もあるため、経済的配慮と丁寧な説明が不可欠です。このような患者対応スキルは、薬剤師の市場価値を高める要素となります。転職時には、こうした実務経験を具体的にアピールできると良いでしょう。
2025年薬機法改正で調剤業務の外部委託が可能に
影響度:2025年の薬機法改正により、一定の要件を満たす薬局間で、一包化や錠剤分包などの調剤補助業務を委託できる制度が法制化されました。これにより、薬剤師は対人業務により多くの時間を割けるようになります。また、安定供給管理責任者の設置義務など、医薬品供給不足問題を解消するための見直しも行われています。
調剤業務の外部委託により、薬剤師の業務内容が大きく変化する可能性があります。単純な調剤作業から解放され、服薬指導や薬学的管理など、より専門性の高い業務に注力できる環境が整いつつあります。キャリア形成においては、対人業務のスキル向上がより重要になるでしょう。転職先を選ぶ際は、外部委託の活用状況や対人業務重視の方針を確認することをお勧めします。
電子処方箋による医薬品供給トラッキングシステム開発中
影響度:厚生労働省は2025年、医薬品の製造から患者への調剤までを追跡できる新システムの開発を計画しています。電子処方箋管理サービスのデータを医薬品会社や卸のデータと組み合わせ、ほぼリアルタイムで医薬品使用状況を把握できるようにします。ただし、2025年1月時点での電子処方箋対応率は病院3.9パーセント、診療所9.9パーセント、薬局63.2パーセントにとどまっています。
電子処方箋システムの普及は、医薬品供給管理の効率化だけでなく、薬剤師の業務スタイルも変革します。デジタルツールを活用した需給予測や在庫管理のスキルが、今後の薬剤師に求められるようになるでしょう。IT活用に積極的な職場環境を選ぶことが、将来的なキャリアの幅を広げることにつながります。
医薬品供給不足の現状:約22パーセントが通常出荷されず
影響度:2025年2月18日時点での厚生労働省の発表によると、通常出荷されていない医薬品の割合は約21.9パーセントで、そのうち後発医薬品の割合が約60パーセント、先発医薬品や長期収載医薬品も12.7パーセントという状況です。供給不足の主な原因は、2020年頃より顕在化した後発医薬品メーカーの品質問題による行政処分、原材料確保の困難性、製造設備の老朽化などです。
医薬品供給不足の長期化は、薬局経営にも影響を及ぼしています。在庫管理の複雑化や患者対応の増加により、業務負荷が高まっている職場も少なくありません。転職を検討する際は、医薬品供給不足への組織的な対応策(複数卸との取引、代替薬リストの整備、スタッフ教育体制など)が整っているかを確認すると良いでしょう。